ショートショート
ジムグリの切望 by 勇智イソジーン真澄
正午を少しすぎて、工藤響子は、待つ人の誰もいない自宅にもどってきた。
昼食にとコンビニで買った鮭入りのオニギリをほお張りながら、居間の円卓に置いてあるパソコンを起ち上げた。出がけに見た赤い生き物が気になり調べてみようと思ったのである。
午前11時から始まる転職のための面接に向け早めに家を出た。車なら30分もあれば着く場所だ。玄関を出、亀の甲羅のように湾曲した大きな一枚石の庭石に足を下ろすと、池に面した端に鮮やかな赤い色の物が動いていた。
目を凝らして見ると小さなヘビのようだった。
恐る恐る、もっとしっかり見ようと前屈みになった瞬間にクシャミが出た。その音で、生き物は素早く地面と石の隙間に隠れてしまった。すすきの花粉が飛散期になると発症する花粉症が始まったのだ。こんな大事な日に鼻水や目のかゆみで集中力が途切れなければいいのに、でも赤いものを見たから心強い、と思いながら面接に臨んだ。
いざという時に緊張し、目がおどおどして、卑屈な落ち着きのなさを醸し出してしまう。そして言いたいことの半分も言えない性格はいまだに改善されず、数人の派遣切りの際にも、残りたいと強く言えず「私はどちらでも……」と答えていた。
案の定、響子は職を失い今に至っている。
今日も、面接官の普遍的質問に対して用意していた答えをすらすら言うことができなかった。じき35歳になろうとしている。年齢的にも条件は悪くなる一方なのに、自らを主張できないのも悲しい癖だ。ため息をつく面接官の仕草で、不採用は目に見えていた。
赤は縁起のいいものではなかったのか。確か夢占いにあったはず。そう思いながら縁起のいい赤を検索したら「赤富士」と出た。ヘビではなかった。もしかしたら今日こそは、とゲン担ぎにしたかっただけなのかもしれない。
響子はもう一度検索窓に「赤くて小さいヘビ」と打込んだ。
《森林性のおとなしい無毒ヘビ。ナミヘビ科ジムグリ(地潜)の幼蛇。夜行性が強く、また半地下性の強いヘビなので昼間には滅多に見かけることがなく、おおよそあまり見かけないヘビという通説がある。子ヘビの背面は赤みが強いが成長とともに色彩斑紋が目立たなくなる》とある。
地面に潜っているからジムグリなのか。響子は自分の化身のようだと思った。
数か月前から参加したfacebook画面に移動すると、友達リクエストが届いていた。思いもかけない、なつかしい名前だった。どきどきしながら、響子は承認するボタンを押し返した。
翌日、facebookを開くとメッセージが届いていることを知らせる赤い数字があった。
送信者は、久保田譲二。
「やっと見つけた。覚えていますか? ジョージです。ネットで検索したりして響子を探してたんだけど見つかって本当に良かった。神様に感謝です。響子にたどり着いて幸せです」
まさか! 探していたの? 私を? どうして? 友達申請だけなら社交辞令みたいなものと考えていたが、あまりの出来事に響子の動悸が早くなる。舞い上がる興奮。心が喜びでいっぱいになり、溢れる想いが止まらないのに、言葉少なに響子は返信した。
「ジョージのこと忘れるわけがないよ。探してくれていたなんて夢みたい。こっちこそ見つけてくれて、ありがとう」
響子は本当に忘れたことがなかった。響子の初恋。一途に恋した青春の人なのだ。
譲二は響子より3歳上だったから、37になる。別れの原因のひとつになったあの人との間には、子どももいるのだろう。連絡が来たことは嬉しいのだが、いまさらどうしたのだと妙に覚めた気持ちも響子の中にはあった。
「元気でいてくれて感謝が溢れます。響子のことを思うたびに、身勝手な自分に腹が立ちます。響子と、人生を語り合う機会が持てたらいいのだけど……」
これまでかかわってきた男たちは幾人かいたけれど、譲二とそうであった20代前半に足繁く通った部屋は、不動産業を経営する譲二の父親の所有するマンションの一室だった。響子は、譲二と一緒だと、どんなに些細なことでも楽しくて仕方がなかった頃を思い出していた。そして、譲二はこんなことをこんな風に言葉にする人だっただろうかと十数年前に想いを馳せた。
1ヶ月の間に響子と譲二は、ほぼ毎日メッセージを交換し、互いの近況を伝えあった。過去に置き去りにしてきた何かに、とりつかれたように饒舌だった。
響子は、譲二と別れた後に、東京を離れたくて山梨で一人暮らしをしている母方の祖母の家に移り住んだ。その祖母が一年前に亡くなり、そのまま一軒家に一人で住んでいる。
譲二は、かつて響子と鉢合わせしたあの人とは離婚し、子どもはいないこと、父の会社で働いているとのことだった。
この部屋で一緒に暮さないか、と譲二が言った時、響子は、私はどっちでもいいよ、と煮え切らない反応をした。譲二にとってはプロポーズだったが、響子はもうひとりのあの人に遠慮していた。本当は嫉妬や悔しさもあった。
あの頃から響子は、素直な気持ちを心の半地下に隠してしまう、おとなしい無毒なヘビのようだった。
メールのやり取りを繰り返しているうちに、響子は少女のように、わくわくした感傷に浸っていた。送信ボタンを押すたび、まるで打ち出の小槌を振ったように、心は恋い焦がれたころに戻っていく。
「会いたい。会いたいよ、ジョージ……」
キーボードは打ち出の小槌のようだ。声に出しては言えない、歯の浮くような言葉にも指を正直に動かしてくれる。あの頃には伝えられなかった想いのすべてを吐き出させてくれる。
「僕も会いたい。会ってくれますか」
譲二からの返信に、響子は浮き浮きする気持ちを思いだしていた。
寂しがりやで調子のいい譲二だった。離婚の痛手から逃げたくて昔を懐かしんだのだろうか。響子は、この一連の出来事が、はかないひとときの夢なのかもしれないと思った。けれど夢でもいい、もう一度私を好きになって欲しい。譲二が見つめる先が希望に満ちていて、その中に自分もいて、少しでも幸せを感じられたならそれだけでいい。
響子は切望した。
クシュン。秋の風が植物の受粉を助けるために、花粉を運んでいる。手提げかばんからティッシュをとりだしながら響子は考えていた。これからは決して逃げずに何事にも立ち向かおう。臆病で内気な殻から脱皮して強くなっていこう。
新しく書いた履歴書をポストに投函し、響子はその足で譲二と約束した場所に向かうため、駅に向かった。
響子はジムグリの幼蛇のように、ふたたび鮮やかな人生の色を放とうとしていた。
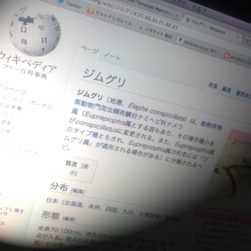
 HOME
HOME