小説(雪 ひつじ ◆流行語◆)
スノーファイト by 勇智真澄
雪が襲って来る。
まるでスターウォーズのオープニング画像みたいに、ヘッドライトが照らす闇から流星のような雪が向かって来る。雪は暗闇から途切れることなく現れ、白い無数の粒で車を飲み込むかのようにぶつかっては後方に消えていく。
久美子はハンドルを操りながら、モノクロのそれを吸い込まれるように見ていた。
どんどん流れてくる雪の中心を見ていると目が回りそうだ。そして車がいま、進んでいるのか止まっているのか、はたまた宙に浮いているのか分からなくなる。
港町側から峠を一つ越えると新興住宅地として発展した町がある。関東近郊とは違い規模は格段に小さいが、田舎に住む人たちも便のいいところ、あるいは親元から独立した家庭を望む人が多くなってできた地域。
久美子は除雪された雪で道幅が狭くなった新興住宅地の車道に車を止め、黒い外壁に「後藤」の文字が刻まれたステンレス製の表札のある、門扉だけが赤い瀟洒な一軒の家の窓を眺めていた。
近隣の人たちはすでに家路についている時間。車道には帰路についた車のタイヤ痕がワッフルみたいな模様で凍り付いていた。
しばらくすると一階の居間であろう場所の灯りが消えた。
久美子は車から降りボンネットに積もった雪を手に取り、右手に悲しみを左手に憎しみを込めてギュッと握り、硬いおにぎりのような雪玉を作った。そしてカーポートに二台並んで止まっている車の一台、見慣れた拓馬のワゴン車にぶつけた。
いくら投げつけても独りよがりの雪合戦で、引き止める言葉を、抱きしめてくれる温かい胸を、何かにすがるように待っているが手ごたえはない。こんなことをしていても虚しいと、わかっていても久美子はここに来ることをやめられずにいた。
今日も、その家の二階の部屋の灯りが消えるのを見届けて、峠道を引き返す途中だった。
拓馬と生活する夢を見て自分の元にいて欲しいという欲望にかられた歪められた虚構。
あの時のあの楽しい時間が、まだそのまま続くと思っている虚構。
それができない、ありのままで、あるがままの現実。
虚構と現実を繋ぐ峠道を行ったり来たりするたびに、久美子は自分も宙に浮いたままだと思った。
対向車がハイビームにしたライトを点滅させクラクションを鳴らしている。
吹雪いた時のハイビームは雪に光が反射して余計に前が見えにくくなるから、本来ならばロービームとフォグランプを点けるはずだ。それを敢えてハイビームにし注意を促してきたのだから、かなり焦っていたのだろう。
その、ほの明るい光と三回目を長く響かせた警告音で、自分の車が中央に寄りすぎていることに気付き慌ててハンドルを切った。ブレーキを踏んだことでタイヤが滑り、赤と白のボーダーに塗られた棒にぶつかりそうになった。等間隔で打ち込まれているこの棒は除雪作業車やドライバーに路肩や崖の位置を知らせる目安となるマーカー。ガードレールも雪に埋まり、崖や曲がり角などがわからなくなるからだ。
久美子はスピードを出していなかったので、かろうじて道路からはみ出さずに止まることができた。交通量が少ないとはいえ夜の峠道、特に冬はしっかりと雪面に注意して運転しなければ危険なのだ。それなのにむかって来る雪に、晴れない心の中から現れる夢と虚構を見てぼんやりとしていた。
「どこ?」
シャワーを終えた拓馬がバスタオルを腰に巻き、部屋をうろうろしている。
「なにが?」
久美子は拓馬のローライズブリーフを穿かせたクッションを横目に見て笑いを堪え、無関心を装って答えた。
「おれのパンツ」
「知らないよ」
青と赤のハワイアンキルトのカバーに、拓馬のブリーフの色がうまくマッチしている。
時にはクマのぬいぐるみの頭に逆さにかぶせて耳をだしておいたり、照明器具に引っかけたり、拓馬がバスルームから出てくる前にブリーフを飾りつけした。簡単に見える場所だけれど、まさかこんなとこに、というところに晒して隠す。探している時間は短いけれど少しでも拓馬の帰りが遅くなればいい……いつもの習慣だ。それを見つけると拓馬は大笑いしてくれる。
「くーは子どもみたいだな。飲み屋のかみさんには思えないよ」
自分より5歳上の拓馬の方が子どもみたいだと、久美子はその無邪気な笑顔に夢を見ていた。
久美子が27歳の時、母親が再婚したために譲り受けた家の一階を改装して[あったかおもてなし料理くう]を三年前にオープンさせた。久美子の愛称のくーと、食う、との意をかけて店名を[くう]にした。カウンターだけの店は10人で満席になる。
客筋は場所柄、農業や漁業関係の人が多く、客がはける時間が早いので開店時間は早めにしていた。
拓馬はオープン当時からの客だった。店の客としては珍しいサラリーマンで、よく同僚と来ていたのだが、いつの間にかひとりで来ることが多くなった。
「かみさんがフラミンゴに夢中になってさ」
「フラミンゴ?」
「そう。こうやって踊るやつ」
胸の前で両手を波打たせて拓馬が言う。
「あ~、フラダンスね」
久美子はクスッとふきだした。
「おれなんかそっちのけよ。くーちゃん、さみしい男なの、おれって」
酔いの回ってきた拓馬は、飲み干したぐい吞みをコツンとカウンターに置いた。
ぐい吞みを下げようと伸ばした久美子の手を、酔いに任せてなのか拓馬が握ってきた。酔っ払いの客には慣れていたし、やんわりとかわす術も身についていた久美子だが、拓馬に触られても嫌な気がしなかった。それより、恥ずかしかった。
吹雪がおさまった頃を見計らい、久美子はゆっくりと車を動かした。他に走行している車もなく、ヘッドライトの灯りだけがぼんやりと前を照らしている。
もうすぐ峠道から国道に合流するという地点で再び地吹雪が舞い、いくつもの白い塊が羊の群れみたいに道を渡っていく。拓馬を好きになって、おとなしい羊になっていた私の群れだと久美子は思った。そばにいて、私のそばにいてと羊の歩みのように力なく歩いている自分だと。
雪は上からも下からも舞ってきて、視界のどこもかしこも真っ白になるホワイトアウトになってきた。
店が休みの日、久美子は拓馬と拓馬の車で港に出かけ、荒れる海を眺めていた。
「俺たち、もう会わないほうがいいんじゃないか」
付き合いが二年になろうかという時に、拓馬がそう切り出した。
結婚五年目にして子供ができた拓馬は、店に来る回数が減り始めていた。待ち望んだ妻の妊娠が夫婦の絆を回復させていた。自分にとって何が最も大切なのか見つめ直したのだろう。
久美子は突然の言葉に頭が真っ白になった。いや、突然ではない。いつかはこんな日がくるだろうと思っていた。別れなければいけないことになることは分かっていた。
「もろい愛なんて長続きしないよ。そんなものにすがりついて夢をみるなんて、だめよ、だめだめ」
けんもほろろに友人の美香に言われた言葉を思い出した。
「このままじゃ、くーがつらいだろ。いい思い出を作ってあげられなくて、ごめんな」
拓馬の声が打ち寄せる波のしぶきのように凍結し、久美子の心に漂着した焦燥がアワ状の波の華になった。
「優しくなんかしないで……。あなたの心の中に私は住んでいなかったのね」
そう口に出せずに、久美子は涙をこらえるのが精いっぱいだった。
突如暗くなった空から大粒のあられが落ちてきて、アルミ箔のドームの中で炒られたポップコーンみたいにパンパンと車のボディを叩き始めた。久美子の気持ちが行き場をなくして破裂しているように。
久美子はホワイトアウトの中を慎重に、しっかりと雪面を確認しながら峠道を抜け出した。
会えなくなって幾日も、久美子は閉店後に拓馬の家の灯りを見ることが日課になっていた。それは今日で終わりにしよう。久美子の心に住み着いた冬は雪解けを待っている。
冷たくなった気持ちを、雪玉に丸めて投げ初めている。ひとりだけのスノーファイト。思いをぶつけたり、寂しさにぶつかったり、もう何も願わないように、そして押し返してくる名残を避けるように、自分の気持ちと雪合戦をしている。
「じゃあね」
最後のひと玉に心の迷いを閉じ込め、拓馬への思いを払いのけるために、そして新しい季節に向けて、それを力いっぱい遠くへ飛ばした。
投げ飛ばした瞬間、久美子は自分の心の整理ができたような解放感を覚えた。
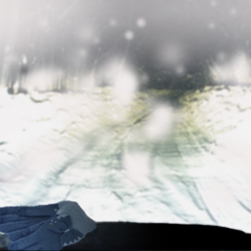
 HOME
HOME