ショートショート
【博士と助手】お笑い質量保存の法則 by 夢野来人
「おかしいな」
「どうしたんですか、博士」
「どうも腑に落ちない」
「何がですか、博士」
「いや。人口じゃよ、地球の人口」
「68億5000万ぐらいでしょう」
「1960年には30億ぐらいしかいなかった」
「目覚しい発展じゃないですか」
「問題は質量じゃよ」
「質量?」
「そうじゃ。1960年に30億だった人口は、1999年には2倍の60億になっており、今や70億に届こうとしておる」
「良いことではありませんか」
「仮に、1人の人間の重さが30キロだったとしよう」
「私はそんなに軽くはありませんよ」
「仮にじゃよ、仮に。すると、30億の人口が増えると重さは何キロ増えるのじゃ」
「900億キロぐらいですね」
「そうじゃ、39年間で人類は900億キロの重さが増えているということじゃ」
「それは大変だ。地球が傾いてしまいそうですね」
「しかし、質量保存の法則に従えば、地球の総質量は変わらぬはずじゃ。人間が900億キロ増えているならば、同じ質量の900億キロ分の何かが減っていなければおかしいじゃろ」
「確かにそうですね」
「そこでわしは考えた」
「良からぬことをですか」
「違うわい。目に見えるもので900億キロもの質量が減ってしまえば、いくらなんでもわかるじゃろう」
「ということは」
「目に見えぬものが減っていると考えるべきじゃな」
「目に見えぬものなんて、博士も科学者らしくないですね」
「何を言っておる。磁力にしても、重力にしても、目には見えぬが存在しているものなどたくさんあるのじゃ」
「磁力や重力に質量があるとは思えませんが」
「ブラックホールがあれば、ホワイトホールがなければ宇宙は存在できぬのじゃよ」
「つまり、人口が質量を増やし続けるならば、質量を減らし続けるものが存在しているはずだということですね」
「そのとおりじゃ」
「それは、見つかったのですか」
「ああ、おおよその見当はついておる」
「すごいじゃないですか、博士。それが証明されれば、ノーベル賞も夢ではない。しかして、その正体は」
「キーワードは循環じゃ」
「と申しますと」
「良いか。水を例に取ってみよう。雨が降ると川を流れ、やがて海にたどりつく。その間にも、蒸発して大気中の水分となる水もあるのじゃが、まあ海に流れるとしよう」
「ええ。流れますね」
「海に流れた水は水蒸気となり、雲を作り雨を降らす」
「確かに循環していますね」
「形を変えて循環していれば、質量は変わらないんじゃよ」
「言われてみれば、もっともな話だ」
「では、人間はどうじゃ。生まれてから、体重が増えていく」
「それは、食べ物を摂取するということで、説明が付きそうですね」
「死んでからはどうじゃ」
「日本の場合、火葬をするので灰となります」
「そのときの質量は?」
「変わってはおかしいですよね」
「重かった死体が軽い灰になる」
「でも、質量は変わらないはずですよね」
「なぜなら、エネルギーに変わるからじゃよ」
「エネルギー?」
「そうじゃ。言うなれば、炭みたいなものじゃな」
「なるほど。重さのある炭が燃えると軽い灰になる。そのときに、炭の質量はエネルギーに変換されているのですね」
「そうじゃ。そのエネルギーが雲を作り、雨を降らせ子供を作る」
「そうか、そういう循環だったのか。でも待ってください。なんで雨が降ると子供ができるんですか」
「若いカップルが雨宿りをする場所と言ったら、きっと子供ができやすいところなんじゃろう」
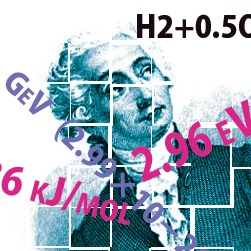
 HOME
HOME