ショートショート
【博士と助手】大発明!問題解決装置 by 夢野来人
博士と助手は、今日も熱心に研究に取り組んでいた。
「博士。今回はどんな装置を作っているのですか」
「聞いて驚くなよ」
「聞かねば驚けませんけど」
「補考器じゃ」
「ああ、歩行器ですか。赤ちゃんが歩くのを助けるあれですね」
助手の頭の中では、歩行器に入っている赤ちゃんがヨチヨチ歩いている。
「だから、おまえはいつまでたっても赤ちゃんのおつむと言われるんだ」
「おむつなどしていませんよ」
「おむつじゃなくて、おつむ。つまり、頭のことじゃよ」
今度、おむつが必要になるとしたら、間違いなく博士の方が先である。
「頭がどうしたんですか」
「どんな難問でも、自分に代わってより良い解決策を考えてくれる問題解決装置じゃよ」
「なるほど、それで補考器ですか。論理的思考を補ってくれる装置ということですね」
「そうじゃ。まだ、試験段階じゃがな」
「では、実験が必要ですね」
「その通りじゃ」
そう言うと、博士の眼球は辺りをぐるりと眺め、ある一点で静止した。
「ダメですよ。ダメダメ。今回は誰がなんと言おうと、私は実験台になどなりませんよ」
「ははは。心配せんでも良い。今回は、わしが自ら実験台となるつもりじゃ」
「怪しいですね、博士。いつもは何だかんだ理由をつけて私を実験台にするのに。もしや、極秘任務があるのではないですか」
「もちろんじゃ」
いつもながら博士の極秘任務とは、たわいのないものである。人に知られると恥ずかしいため極秘になっているが、重要だった試しはない。
「冷たいなあ。教えてくださいよ。任務しだいでは、私がその危険な実験台になろうではありませんか」
そのたわいもない極秘任務が、助手はたまらなく好きであった。
「いや、今回は良い」
「またまた。ますます怪しい。よほどの極秘任務なのでしょうね。教えてくださいってば」
「人に知られぬから極秘なんじゃ。おまえに教えてしまっては、極秘じゃなくなってしまうじゃろ」
「わかりました、わかりました。では、教えてくれなくても結構です。そのかわり、せめて実験台には私を使ってください」
「そこまで言うなら考えてみるが」
「やったー。これで、私が栄えある実験第1号ですね」
飛び跳ねて喜ぶ助手をわき目に、博士は一枚の紙きれを見つめていた。
「効果は絶大じゃな」
助手も博士の様子に気がついたようだ。
「博士。手に持っている紙きれはなんですか」
「補考器が出力した指示書じゃ」
「なんですか、それ」
「つまり、実現したいことを補考器に入力すると、このような指示書が出力されるのじゃ。あとはそれに従うだけで、実現できるという仕組じゃ」
「紙で出力されるとは、なんとも博士らしくアナログ的ですね。でも、本当に効果があるんですか」
「ああ。今証明されたところじゃ」
「えっ。博士の実現したいことって、なんだったんですか」
「知りたいか」
「ええ、ぜひ」
「実験台になるのが嫌いな助手をその気にさせる方法じゃよ。ほっほっほ」
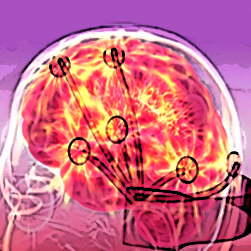
 HOME
HOME